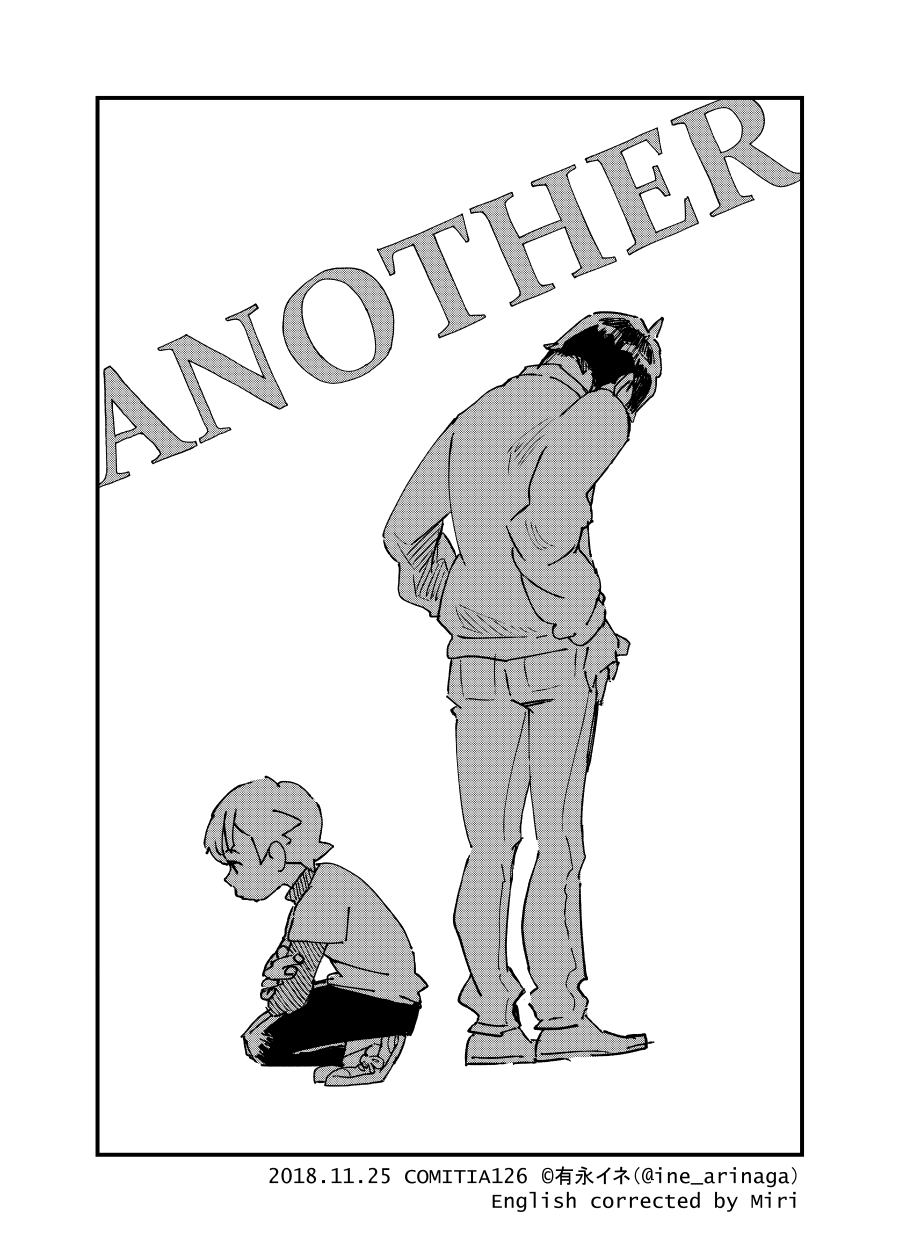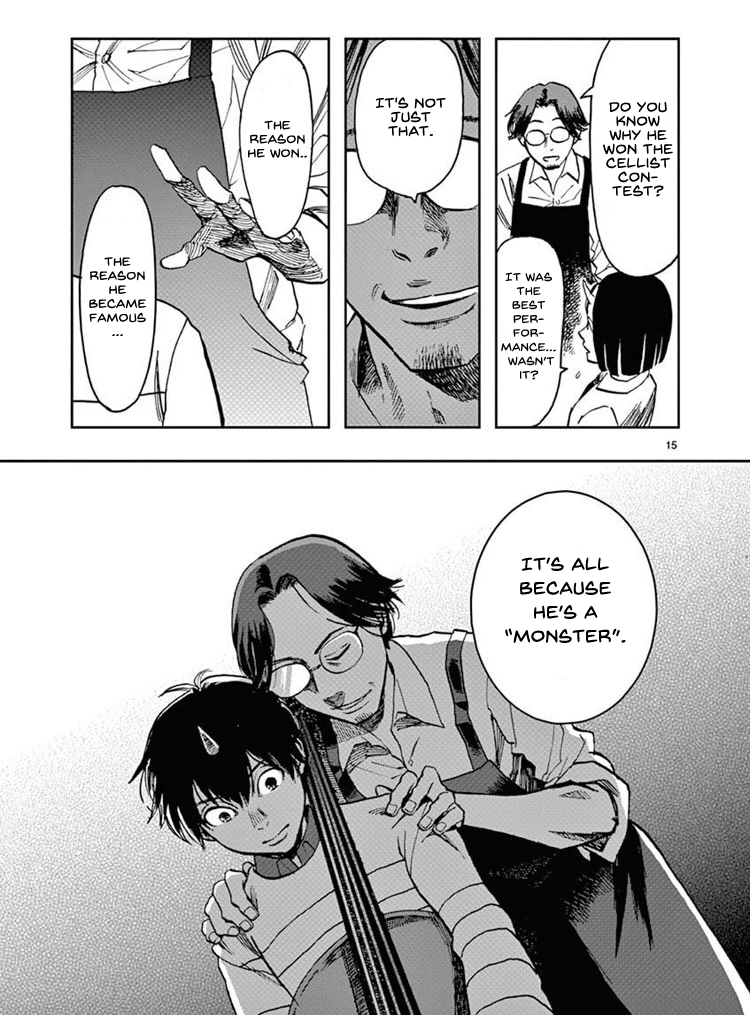ずっと英語の悪夢を見ていた。
海外から帰国してもう十数年間、3日に1回くらいかな。
悪夢というのはなかなかやまない。結構律儀なもので習慣になる。
見ていると「ああまたか」と思うし、見終わったあとも「まただったな」と思う。涙をぬぐいながら。
私にはいくつか涙を流すほどの悪夢がある。
その中の一つの悪夢が、一年前に消えた。
2019年の最後に、その話をしようと思う。
悪夢が終わりを告げる日というのに、人間はそう立ち会えるものではない。
立ち会った。
2018年12月15日。
1年ほど前。
今年の話でなくて申し訳ないけど一年前ということで今年の範疇内として許してほしい。
夢を見た。
それは澄んだ水がこんこんとわきだす池のあるインターナショナルスクールだった。
壁は透き通ったガラスでできていて、その向こうには赤と青の二層の色が見える。
砂漠と空。
灼熱の赤い大地に目がくらむような青いとろりとねばりつく濃い青色の空が覆いかぶさっていた。
熱帯特有の頬の横を焼くような暑さ。吸い込む熱気は無臭のはずなのに独特の「熱帯」の匂いを持っている。雨はもうしばらく降っていないだろう。なんとなくそんな気がする。
床もガラスでできている。私は裸足でガラスの階段を登りながら、ガラスの椅子に腰掛け、ガラスの机にテキストを広げた。
ここが今日から私の新しい学校なのだ。
ここが今日から私の脅威の中心なのだ。
1st period(1限目)は物理の授業。
物理の先生は肌の濃いアジア人の女性の先生で、肌の色は砂漠にとても似合っていて白目がとても明るく、闇夜に光る目が私をきっと睨んでいた。
「お前の名前は何という」
「私は――といいます」
私は自分の本名を答える。すると彼女は鼻で笑う。
「どうしようもない名前だ。お前には別の名前をつけないといけない。糞だか、アホだか、そういうもっと呼びやすい名前を」
「……はい」
はいなんて答えてしまうべきではないはずなのに、答えてしまう。それが正しいような気がしたのだ。
だってここはインターナショナルスクール。私がこの十数年夢の中で脅かされ続けてきた場所。勝てっこないのだ。NOなんて言葉、この逃げ場のない砂漠に囲まれたガラス作りの学校には存在しないのだ。
「お前の英語は本当にへんなアクセントをしている。何か話してみろ」
「すみません」
「ほら変なアクセントだ。みんな聞いただろうか? 今なんと言ったか聞き取れた者は?」
笑い声にうつむく。ガラスでできた机は私の膝を透かして映す。その向こうにある燃えるような赤い大地も私の脚を縁取る。
「お前は残念ながら女だ」
前の席の少年が私を小突いた。彼はのちに別件で逮捕される。
「言葉が話せない女だ。ボールをぶつけられても自分が悪いと謝るなんて日本人はdeafだな」少年は笑う。
「お前は暴力を振るわれた時に謝るのか。ではそれはお前が悪いのだ」教師も笑う。
そうなのだろう。
私が悪いのだろう。言葉も話せず、やり返すこともできない私が悪いのだ。
「そんなお前が生きている意味とはなんだ。説明ができないだろう。説明ができないということは生きる資格がないのだ。わかるか?」
わかると思う。
この十数年、数日にいっぺん同じような夢ばかり見てきた。
私はこの夢を何度も見てきた。インターナショナルスクールにいるときから見てきた。実際にあったことを象徴化して反芻している夢だ。
この夢はそろそろ終わるだろうと私は知っていた。
起きたら泣いているだろうということも知っていた。
“I’m sorry” “I can’t”
と叫びながら目がさめることもあるだろうということも承知していた。
いつもの夢。いつもの脅威。いつもの悪夢。何百回目の無力感。
私が自分の膝をぼうっと見つめていると声がした。
「先生、それは違うと思う」
顔を上げると私の隣に見たことのない生徒が座っていた。
ヨーロピアンだったと思う。私の記憶にはない生徒だった。彼女は赤毛混じりのブロンドで、背をぴっと伸ばして、鼻の上にすこしだけそばかすをのせていた。知らない少女だった。
「それは違う」
彼女はもう一度言った。
その少女と面識はなかった。けれどその横顔をよく知っていると思った。
私が今よく会っている日本在住の、私の愛しているドイツ人とアメリカ人の友人に似ていた。彼らはおとなになってから知り合った。インターなどにいるわけがなかった。なにより彼らは2人の人間であって、1人の人間になりうるわけがない。
私は何度かまばたきをした。まばたきをするたびに少女はドイツ人の友人になったり、アメリカ人の友人になったり、ふんわりと面影を異にした。
なんで彼女たちがこんなところに。”こんなところに”いるのかわからなかった。
わからなかったけれど、私はその少女を目にした瞬間に「ああ、わかったよ」と思った。
ぼんやりと熱気で霧がかかり物事があいまいだった赤と青の世界が、ゆるゆると輪郭を持っていく感覚に陥る。
「先生」
私は顔をあげた。
チョコレート色をした顔の教師と目があう。闇夜の目が私を静かに見つめ返す。
恐ろしい。
恐ろしいけれども。
「先生。私は、悲しかった。自分の人種や性別に対してそういうことを言われて、この十数年間ずっとずっと悲しかった。ずっと怒りを感じていた。私はそういうことを言われて苦しむ全ての人間の味方です。私を含めた、味方でありたい。だから私の名前は私が決める。あなたじゃない」
はっきりとした発音の英語でゆっくり言った。
教師は何も言わなかった。
反論もしなかった。怒りもしなかった。表情も変えなかった。
ただ私の言葉をじっと聞いていた。
ふと視線を感じて振り向くと、インターナショナルスクール時代に同期だった生徒たちが立っていた。
全員と目があった。懐かしい少年と少女たちばかりだった。
彼らは少しうなずいて、私ににっと笑ってみせた。grin、だ。
私もgrinした。
池からこんこんと湧き出た水は今やあふれ出して足をぬらしていた。
それはどんどん赤い砂漠を覆い尽くして青く染めあげ、青い空と近づこうとしているように見えた。
そこで目が覚めた。
起きた時、右目から一筋だけ涙が流れていた。
「呪いが解けたのだ。もう悪夢は見ないだろう」
と誰に教えられるわけでもなく知った。
私は当時のWEBサイトで海外生活を見守っていてくださった方がいたことへの感謝をこめてこの夢のことをTwitterに書き、ドイツ人とアメリカ人の友人にもより詳細な夢の英訳をメッセージにして送った。なんだかわけも分からず朝からみんなで泣いた。
彼女たちのおかげだった。返せない恩がまたできてしまったと思った。
かくして私は本当に悪夢を見なくなった。
1年経つが未だに一度も見ることはない。
英語の夢を見ることはあっても、独米の友人たちとどこにいこうかと話したりする穏やかな夢ばかり見るようになった。
悪夢というものが終わる瞬間はこんなにあっけない。
そっけなく、同時に私にとってはドラマチックであり、やはりささやかな出来事でもあった。
だいぶ時間がかかってしまった。けれど「やりきったのだ」と思った。何をかは知らないけれど。
やさしさの中で生きていると思う。
そう思えた1年だった。苦しいこともあったけれど、そこにかならず優しさのピースがはまってくれた。
悪夢はいつか終わるのだ。
こんな定型句を言える日がくるなんて。
ありがとう。
ずっと誰に向かってかはわからないけれど、そう思って暮らした一年だった。
また来年も。